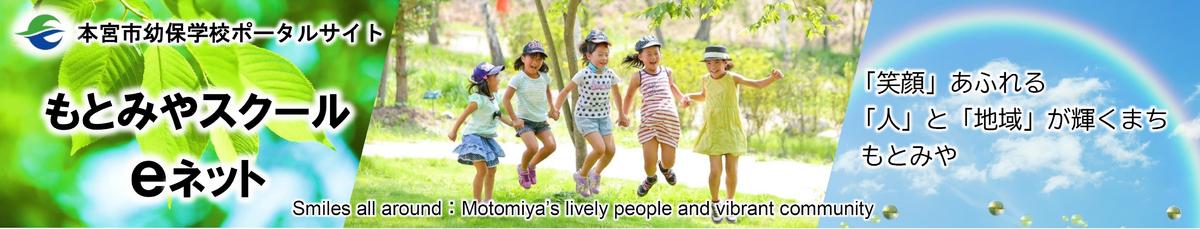糠沢小の日々
本年もよろしくお願いいたします。
本校のホームページをご覧いただきありがとうございます。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
先日、白沢公民館を会場に、「本宮ふれあい書き初め大会」が開催されました。本校からも、3年生2名、4年生4名、5年生5名、6年生3名の14名が参加しました。
少しでも納得のいく作品を仕上げようと、よい緊張感の中で、真っ白い用紙に一画一画心を込めて書く子どもたちの姿はとても素晴らしいものがありました。


この「本宮ふれあい書き初め大会」では、書き初め大賞1名、特選1名、金賞1名、銀賞2名、銅賞2名と、半数の子どもたちが賞をいただきました。こういった地域の活動に積極的に参加し、自分のよさや可能性を伸ばそうと一生懸命に頑張る子どもたちは、本校の宝です。
よさや可能性がキラリと輝いた2学期が終了!
22日(木)、80日間の2学期を締めくくる終業式が行われました。
式では、校長先生から、冬休みの生活で特に心がけてほしいこととして、「健康に気を付け、命を大切にすること」「計画的に学習を続けること」「お手伝いをたくさんすること」というお話がありました。
続けて、児童代表3名が、「2学期を振り返ってと冬休みの抱負」についての発表を行いました。できるようになったことや頑張ったことの紹介がたくさんあり、充実した2学期だったことがうかがえました。そして、「家の手伝いをする」「勉強を頑張る」と、明日から始まる18日間の冬休みを楽しみにしている様子が分かりました。


また、冬休みの過ごし方について、生徒指導の先生よりお話がありました。
「立派な大人になるために」はどんなことを心がけていけばよいのか、NHKの大河ドラマ「八重の桜」一躍有名になった山本八重(新島八重)の生き方、その生き方の礎となった「什の掟」を取り上げてお話されました。『ならぬことはならぬものです』などの先人の教えを意識させ、よい冬休みにするための約束を確認しました。




この2学期は、校内水泳大会での一人一人の頑張りから始まり、自己ベストを目指して走り抜いたマラソン大会、最高の思い出を創り上げた学習発表会など、171名全員で同じ時間を共有し、よさや可能性がキラリと光る頑張りと思い出がたくさんできました。やり遂げた充実感・達成感、頑張り抜いた自信が、一人一人をさらに大きくしてくれた学期ではなかったかと思います。
保護者の皆様、地域の方々には、たくさんご協力をいただきました。誠にありがとうございました。
さて冬休みは、子どもたちに学ばせたいことがたくさんある時期でもあります。大掃除、お正月の飾り付けや買い物、おせち料理作りなど、年末の仕事をみんなで協力したり家族団らんのひとときを過ごしたりする中で、家族の一員としての自覚も強まります。一方、大人中心の生活になりやすく、子どもたちはすぐ体調を崩しがちでもあります。小さい時から自分の健康は自分で守る習慣をきちんと身に付けさせたいものです。基本的な生活習慣が身に付くようご助言ください。
3学期の始業式、171名が元気な顔で登校してくるのを楽しみにしています。それでは、ご家族そろってよいお年をお迎えください。
メディアと上手に付き合うために
20日(火)、6年教室では、担任と養護教諭による学級活動が行われました。授業は、「わたしたちの生活と情報」という内容で、メディア漬けによる健康被害を知り、メディアと上手に付き合うための方法を、これまでの生活から見つめ直すという学習でした。
ゲームし過ぎによる脳の状態を写真で見せてもらったり、心に見立てたハート形の模型を用いてメディア利用による弊害について教えてもらったりした後、心のエネルギーがいっぱいになるためにはどうすればよいのか、メディアとのかかわり方を考えました。
「読書をする」「音楽を聞く」「勉強する」「運動する」「趣味に没頭する」「絵を描く」「手伝いをする」「家族と話をする時間を作る」など、今の自分の生活を振り返りながら、心を元気に充実させるために自分ができることをまとめていました。



私たちの生活は、テレビやパソコン、ケータイやスマホ、ゲーム機などとたくさんのメディアに囲まれています。こういったメディアとつきあわない生活は考えられません。これからの情報社会を生きていく子どもたちにとって、メディアとの上手な付き合い方を身に付けることは、健康で安全な生活をするためにも、確かな学力や生きる力を身に付ける上でも、とても大切なことです。
今日の学習で、6年生一人一人が今週から始まる冬休みに取り組む目標を立て、実践へ向けた第一歩が踏み出せたことは、大変意義のある学習になったはずに違いありません。
食べて元気に!
先日19日(月)、5年家庭科の授業研究会が行われ、「五大栄養素のはたらき」を学習しました。
食品にはどんな栄養素が含まれているのか、これまでの生活経験や知っている情報から言葉を出し合い、説明を聞きながら再確認していきました。その後、ごはんやパン、肉や魚などの様々な食品カードを、「炭水化物」「タンパク質」「ビタミン」の3グループに分ける活動を行いました。



「~は~だからここだよね。」と考えを交流させたり、「無機質って何?」と友達に相談したりしながら、班ごとに学習カードにまとめていきました。ウィンナーや油揚げなどの加工食品をグループ分けする頃には授業がどんどん盛り上がり、夢中になって学習に取り組む姿が見られていました。
これで本年度の校内授業研究会は終了となりますが、これからも「学び合い」を生かして、楽しくて分かりやすい授業を実践し、子どもたちの笑顔につなげていきたいと思います。
たいせつなからだ
先日、1年生の学級活動では、養護教諭と一緒に「たいせつなからだ」の学習を行いました。学習では、手作りの人型ボートを使いながら、自分の体にある部位を貼り、男女の違いに気づかせていくところから学習が盛り上がっていきました。そして、大切な体を守るためにはどうすればよいか、友だちと話し合い、進んでワークシートにまとめたり、進んで考えを発表したりする活動へと広がっていきました。


担任と養護教諭の連携により、大切な体を守るために、これから自分が意識して生活していくことは何なのかを、一人一人がもてた良い学習となりました。


鼓笛オーディション
12月上旬から、新鼓笛隊で自分が頑張りたい楽器やパートの自主練習を行ってきた4・5年生は、みんな一生懸命でした。そんな中、先日はオーディションが行われました。たくさんの先生方に見守られた中でのオーディションは緊張したことと思いますが、真剣な面持ちでこれまでの練習の成果を発揮していました。3学期になってから、決定した楽器やパートでの練習が本格的になってきます。希望した楽器やパートに決まった人もそうでない人も、糠沢小鼓笛隊の一人として、この歴史と伝統を引き継いでいき、これまで以上の鼓笛隊をつくってほしいと思います。



6年生が調理実習をしたよ
先日、6年生は、家庭科の学習で調理実習を行いました。学習では、バランスの良い献立を考えるところからスタートし、身近にある食材でおかずを作る実習や会食を通して、楽しくおいしい食事をするための工夫を学んでいくのがねらいでした。



班ごとにおかずを「ジャーマンポテト」と「スクランブルエッグ」の2品を協力し合って作りました。手順を確認したり、野菜の切り方を教え合ったり、味見をしながら味付けをしたりと、みんな笑顔で調理し、どの班もおいしく完成しました。やはり自分たちで作った料理は格別だったようで、楽しく充実した時間となりました。
優しい気持ちがいっぱいの募金が集まりました!
10月1日より全国一斉に行われている赤い羽根共同募金運動に、本校も協力させていただきました。
運営JRC委員会が中心となって全校生に呼びかけ、気持ちのこもった募金が6,825円集まりました。ご理解とご協力ありがとうございました。
みなさんから集められた募金の70%は、みんなの町の福祉活動やみんなが遊ぶ公園の遊具など、みんなの町をよくするために使われるそうです。残りの30%は、福島県で使われるそうです。例えば、大規模な災害が起こった際の備え、大規模災害が起こった際の災害ボランティア活動支援など、被災地を応援するためにも使われるということです。
一人ではできないことも、みんなが力を合わせればできることがあります。私たちの生活は、みんなが一緒に支え合って暮らしています。この募金は、みんなの思いやりの気持ちだと思います。たくさんの思いやりが集まれば、その分、たくさんの人が幸せになれます。言い換えれば、募金は、思いやりの気持ちを目に見える形にしたボランティア活動の一つともいえます。
みんなの幸せを思う気持ちをこれからも大切に育てていきたいと思います。
なぜ手洗いが大切なの?
先日、1・2年生は、給食・保健委員会のお兄さんやお姉さんたちに、手洗いの大切さを教えてもらいました。まず給食・保健委員会から、お話を聞きました。「いつもきちんと手いいできていますか?」「面倒くさいから…という理由で、きちんと手を洗わなかったりしていませんか?」「手には目に見えないバイ菌がいっぱいついていますよ。」と。
そこで、きちんと手洗いができているのか、手にジェルを付けていつものように手洗いし、自分の手を手洗いチェッカーで調べてみました。きちんと手洗いしているのに、洗い残しがあるためにブラックライトで青くなる自分たちの指先にびっくりの1・2年生でした。



今年も風邪やインフルエンザの流行が気になる季節になってきました。風邪の予防には手洗いやうがいが基本だと言われています。普通の石けんと流水で手を洗うだけでも20秒間ぐらいかけて念入りに行えば、多くの場合、十分な手指の洗浄になるそうです。
自分から進んできちんと手洗いやうがいをし、かぜなどをひかず、毎日元気に登校する糠沢小学校の子どもたちを育てていきたいと思います。
地域の伝統に触れる<高松神社「太々神楽」>
11月30日(水)、地域学習の一環として、3年生が「高松神社太々神楽」の体験を行いました。これは、総合的な学習の時間に行う「ふるさと糠沢を探ろう」の学習の取組の一つです。今回は、高松神社太々神楽保存会の皆様にご協力をいただき、実際にこの「太々神楽」を見せていただきました。
本宮市には、糠沢地区にある高松神社の他、春日神社、浮島神社、和田神社、鹿島神社、長屋神社などに、それぞれ本宮市指定無形民俗文化財である太々神楽があり、保存会の方々が次の世代へ伝承しているのだそうです。そして、元旦祭、春季例大祭、秋季例大祭に合わせて練習し、奉納しているのだそうです。






この高松神社太々神楽の保存会には、本校の児童も数名入って練習に参加し、例大祭などにも参加しています。この日は、保存会の大人の方たちと保存会に入っている児童が、太々神楽の演奏と舞を、一緒に披露してくれました。
太々神楽の披露後、太鼓や笛、舞の道具に触れさせていただき、自分たちのふるさとである糠沢の伝統芸能を身近に感じることができました。そして、糠沢地区にこのような歴史と伝統が伝承されていることを知るよい機会ともなりました。
和楽器の魅力に触れる
11月29日(火)、箏曲生田流まゆみの会の会主:上川様を始め、会員の皆様方、そして郡山都山会の武田様をお招きして、5・6年生が箏と尺八の鑑賞・体験を行いました。
生で聴く箏や尺八の音色のやさしさと強弱、曲のテンポの変化など素晴らしい演奏に子どもたちは魅了され、目を輝かせながら聴き入っていました。
演奏の後、箏や尺八の説明や魅力を教えていただいた後、大変高価で貴重な箏を弾く体験をグループごとにさせていただきました。箏は、「さくらさくら」の曲に挑戦しました。弦をはじく場所により音色が変わりとても難しかったようですが、丁寧に教えていただきなんとか演奏にすることができました。6年生は昨年の経験を生かし、上手に演奏できていました。



今回、学校支援地域本部となる生涯学習センターの協力を得て、箏曲生田流まゆみの会の会主:上川様を始め、会員の皆様方、そして郡山都山会の武田様にご指導いただきました。ありがとうございました。
子どもたちは、この貴重な体験を通して、本学習のねらいでもある和楽器のよさを味わうことができました。授業後の感想には、「箏や尺八の音色が素敵だった。」「やさしく教えていただき、音が出せてうれしかった。」「演奏するのは難しかったけど楽しかった。」などと感想を述べていました。
「学び合い」で夢中になって学ぶ子どもたち
本校では、研究テーマに「『学び合う力』を生かして活用力を育てる授業」を掲げ、「協同的な学びによって子ども同士が学び合う日々の授業」を大切に、学び合いをしながら夢中になって学ぶ子どもの姿を目指し、日々子どもたちと真剣に向き合っています。
11月28日(月)には、今年度最後となる第8回授業研究会が行われました。今回は、福島県教育庁県北教育事務所指導主事の湯田公夫先生をお招きしました。また、幼小連携、小小連携、小中連携の取組の一つとして、糠沢幼稚園や白沢中学校の先生方にもご参観いただき、3年理科「明かりをつけよう」の授業公開を行いました。



この授業は、どのようにつなげば明かりがつくのか、つくつなぎ方とつかないつなぎ方を考え、ペアや全体で学び合っていくことで、幅広い思考力をもたせながら電気回路について学んでいく学習でした。


子どもたちの興味・関心を引きつける学びがいのある学習課題が設定され、自分の考えを説明したくなる、友達の考えを聞きたくなる、そんな雰囲気の中で夢中になって学ぶ子どもたちの姿が見られました。
授業後の研究協議会では、県北教育事務所指導主事の湯田先生より、授業のユニバーサルデザイン化がされている授業であったこと、脳(能)が動く「能動的な授業:アクティブラーニング」の授業であったことをお話しいただきました。また中学校の先生からもご助言いただき、児童生徒の実態や指導の在り方などについて学びを深めることができました。校種の段階の役割を再確認し、広い視野に立って授業改善を図っていく有意義な会議となりました。


勉強するのが大好きな子どもを増やし、学力向上につなげるためには、本授業のように、楽しくて分かりやすい授業づくりが大切です。今回、一人一人の思考がフル稼働し、学び合いながら思考力も高まり、学びが深まっていくのが分かる授業に、各先生方は、こんな授業を実践し、子どもたちの笑顔につながるよう日々の教育にまい進したいと、気持ちを新たにする授業公開となりました。
「シェフのおしごと」…プロの料理人の魅力に触れて
24日(木)、日本調理技術専門学校のフランス料理主任の鹿野先生と実習生の齋藤先生においでいただき、6年生に「シェフのおしごと」を体験させてくださいました。
これは、ふくしま職業体験出前講座の一つとして、本校の希望をかなえていただき実現した学習です。学習では、フォアグラのソテー、牛肉のステーキ、デザートと、フランス料理を調理するデモンストレーションや試食、講話を通して、シェフという仕事の魅力や料理作りの楽しさを教えてくれました。


目の前で料理を作る様子を見せていただいたことや様々なお話をいただいたことにより、子どもたちは、「シェフという仕事に興味をもった。」「料理などを作る人になって、たくさんの人に喜んでもらいたい。」「腕を磨くためには、料理の世界でも努力をしなければならない。」「将来は、シェフやパティシエになりたいので勉強になった。」などと感想を述べていました。




子どもたちは、心のこもった料理で人を笑顔にできるプロの料理人の素晴らしさを感じ、職業への意識を高めることができたようです。そして、サービス業=愛情業であるなど、講話も大変勉強になり、キャリア教育のねらいを達成することができました。
いただいた料理はどれもがとてもおいしくて、感動いっぱいの素敵な時間となりました。
鼓笛移杖式へ向けて動き出す!
24日(木)、新鼓笛隊を編成する4・5年生へ向けての説明会がありました。
今回の説明会には6年生も参加しました。6年生には、習得しているパートの演奏や動きを下級生に伝え、歴史と伝統を引き継いでいくという大事な役割があるからです。

4・5年生は真剣に話を聞いており、その熱心に説明を聞く態度から、糠沢小学校の鼓笛を引き継ぐという強い意志を感じる結団式ともなりました。
各楽器等の体験をした後、オーディションを経て新鼓笛隊が編成されていきます。そして、鼓笛移杖式へ向けて、毎週火曜日と木曜日の学級の時間を中心に、上級生から下級生へと、演奏や動き、楽器等の扱い方、手入れの仕方、後片付けを伝えながら、新しい鼓笛隊が引き継がれていくことになります。
歯みがき教室②<1・2年/3・4年>
24日(木)、歯科衛生士さんにおいでいただき、1・2年生と3・4年生を対象とした「歯みがき教室」を実施しました。
1年生は、お口の中の様子を鏡で確認したり、歯の役割を教えていただいたりした後、歯みがきの仕方を学習しました。2年生は、むし歯の成り立ちを学習した後、6歳臼歯の役割を知り、自分の6歳臼歯をさがした後、歯みがきの仕方を学習しました。

3年生は、自分の歯ならびを知り、それに合った歯みがきの仕方を学習しました。4年生は、3年生の学習内容に加え、おやつとむし歯の関係を知り、歯みがきの大切さやブラッシングの仕方を学習しました。
これからも、歯の健康に関心をもち、口腔を清潔にして気持ち良く生活していく子どもたちに育っていけるように、学校と家庭が一緒になって進めていきたいと思います。

学校司書による「ブックトーク」
読書指導の充実のためには、本に親しむ機会を多くすることが大切であり、読書の習慣を身に付けさせ、読書の楽しさや喜びを感じさせていくことがポイントとなります。
そこで本校では、これまでも折に触れて良い本を紹介するなどの取組「ブットトーク」を、しらさわ夢図書館と連携して進めています。
先日は、毎週お出でいただいている学校司書の小林さんに、3年生へのブックトークをしていただきました。お話に引き込まれ、本のもつ魅力を感じる時間となりました。


「しらんぷり」は、『いじめ』と同じだよ
1年教室に、友だちに言われてうれしくなったり元気が出たりする「ぽかぽか言葉」が掲示してあります。1年生だけに限らず全学年で、「ぽかぽか言葉」を進んで使う学級の雰囲気を生み出すとともに、互いに気持ちよく接することのできる人間関係を育てていきたいと考えます。
先日22日(火)、本宮市人権擁護委員の方々においでいただき、5年生を対象に「人権教育」の学習を行いました。今回は、「いじめ」に特化した授業でした。「いじめ」に理由なし。悪いのはいじめる側であることや、見て見ぬふりをすることはいじめていることと同じという話を聞いた後、ビデオを見ました。
一般的に小学生の時期の子どもたちは、自分の気持ちを優先させ、友だちの気持ちを考えないで発言したり、相手に対する思い込みで判断しがちです。それによりトラブルも起きやすいものです。このビデオでは、人の気持ちを考えてもらいたい。いじめは絶対にいけない。見て見ぬふりはいじめだということを、見ているみんなに問いかける内容で、心に響くものがありました。



最後に、『ふくしま子ども憲章』をみんなで読み上げました。「命を大切にする」「ありがとうの気持ちを忘れない」「友だちや家族を大切にする」「夢に向かって努力する」・・・。
今日の学習だけでなく、様々な教育活動の場面で、一人一人の人権意識を育てていきたいと思います。
読書月間です!
「読書好きにするためにはどうすればよいか?」
そのためには、小さい頃から本に親しむ機会を多くすることが大切であり、読書の習慣化と合わせて、子どもたちが読書の楽しさや喜びが得られる読書指導を行っていくことが大切だと考えます。
本校では、本宮市やしらさわ夢図書館の協力を得て、ボランティアの方々による本の読み聞かせや、移動図書館「あだたら号」の巡回、学校司書によるブックトークやアニマシオンなど、子どもたちの読書意欲を引き出す魅力ある取組をしていただいております。大変ありがたいことです。


本校では、11月7日から12月6日までを読書月間として、本に親しむ機会をこれまで以上に増やしています。例えば、図書委員会が企画した「どくしょビンゴ:秋」では、いろいろなジャンルの本を読んでビンゴを完成させると、しおりがプレゼントしてもらえたり、「○○冊読もう」を学級の目標にしてみんなで取り組んでいたりと、読書活動に積極的に取り組んでいます。
子どもたちが夢中になって学ぶ授業を目指して
先日14日(月)、福島学院大学教授の宮前貢先生をお招きして、第7回授業研究会が行われました。今回は、6年国語科の「海のいのち」の授業公開でした。
父を破った瀬の主のクエをうたなかった主人公の太一の心情の変化を、太一の言動や情景描写、登場人物とのかかわりをつなぎながら、太一の心情を変化させたものを読み取っていく学習でした。


自分の考えを自由に発表できる学級の雰囲気、友達の発表に真剣に耳を傾ける姿、自分の考えと照らしながら友達の考えを聞く学びの深い子どもたちの姿など、学ぶべきことが多い見事な授業でした。
また、一人一人の考えや発言を大事にしながら授業を進め、みんなの考えを整理したり関連付けたりした板書も、思考の流れが可視化され、学習のねらいに迫る手立てとなった授業でした。


今回も、担任の熱意ときめ細かい準備や高い指導力が分かる授業であり、子どもたちの言葉をつないで授業をコーディネートする大切さを再確認できた授業となりました。
授業研究会後、宮前貢先生に「協同的な学びを大切にした授業について考える」という演題で講演をいただきました。協同的な学び=学び合いは、学習の本質であり、一人一人の学びを成立させより高いレベルへと導くためには、協同的な学びが不可欠であるというお話をいただきました。そして、どこでどんな学び合いをさせていくのかについて、毎時間の授業の中で友達とかかわり合って学んでいる子どもたちを支えながら、授業実践を積み重ねながら掴んでもらいたいというお話をいただきました。
「授業が変われば学級が変わる」という想いをもって、まずは教師自身が授業を楽しんでいきたいと、明日から授業へ向けて気持ちを新たにする研修会となりました。


自分自身の頑張りに1等賞をあげる走りができました!
16日(水)、一日フリー参観に合わせて、校内マラソン大会が開催されました。
4月から毎日、朝や業間、子どもたちはマラソン練習に進んで取り組み、体力向上を図ってきました。
今日の大会では、気持ちの良い天候の下、一人一人が自己ベストを目指して頑張ってくれました。


入賞を目指して走りたい子、ベストタイムを出そうと意気込み十分な子、遅くてもいいから頑張って走りたい子、本当は走りたくないと思っている子など、このマラソン大会への想いは、一人一人が違います。
しかし、そういうみんなが集まり、一緒になって走る。同じゴールを目指し、自分の弱気な心に問いかけながら、打ち勝ちながら走り抜く。そういった点では同じだと思います。
その一人一人の一生懸命な走りが、見ている友達やお家の方々、地域の方々の心を熱くし、感動を与えてくれた大会となりました。


今日のマラソン大会では、一人一人がこのマラソンの主人公でしたし、たくさんのドラマを創ってくれました。練習の成果を発揮し、ゴール目指して力いっぱい走り、自分自身の頑張りに1等賞をあげられる走りができた子どもたちを頼もしく思います。
保護者や地域の皆様には、ご多忙の折、応援にかけつけ、校庭やコース等で応援をいただき誠にありがとうございました。たくさんの方の応援のおかけで、子どもたちはいつも以上の走りができ、達成感・満足感・成就感をもって、このマラソン大会を終えることができました。